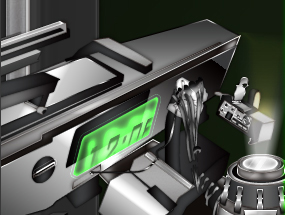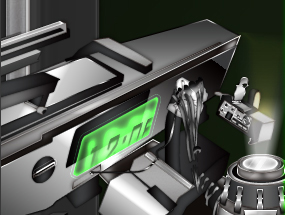|
 |
| 【共鳴】アジト跡から発見されたハーモニウム記録映像 |
「解析? 映像データのですか?」
「そ。この間、ハーモニウムのアジトから見つかったやつをね」
カンパネラ学園──地下研究所──第三キメラ研究室。
ここの研究員であるエリックは、研究室主任の秋桜理(しおり)にコーヒーカップを手渡しながら訊ねた。
「なんでそんなものがウチに?」
「何処の研究室も忙しいからよ」
「ウチも暇ってわけじゃ‥‥」
「私が、見たかったの。何か、文句でも?」
一言ずつ強調された上に眼鏡越しに睨まれては、気が弱いエリックは「いえ別に」と答えるしかない。
「第一、こんな珍品を解析できる機会なんて貴重でしょ?」
「それはそうですが‥‥」
「木っ端微塵になったアジトから、原型を留めた状態で見つかったのよ? つまりはかなり厳重に保管されてたってことでしょ? 何が映ってるか興味あるじゃない」
「まあ、確かに気にはなりますね‥‥」
エリックはコーヒーを一口すすり、同意を示す。
「主任はもうご覧になられたんですか?」
「動作チェックも兼ねて、ちょっとだけね。映像は不鮮明だったけど、音声はそこそこ聞き取れるレベルだったわよ」
「なるほど‥‥」
「さて、無駄口もこの辺にして、再生するわよ」
「今更ですが、僕も見ていいものなんですか?」
「当たり前でしょ。何の為に私の部下やってるのよ。──それじゃ、再生っと」
秋桜理は焦げ茶色の瞳を好奇心で輝かせ、ディスプレイをじっと見つめた。
──‥‥‥‥──‥‥──‥‥‥‥──
なんていうか、すっごい殺風景な部屋よね。
簡素な椅子と長テーブル以外、目立った設備もないし。
自分からカメラを回しておいてなんだけどさ。
ちなみにこの部屋は会議室だったり教室だったり休憩室だったりと、時と場合に応じて用途が変わる。
つまり、私たちは相当な時間をここで過ごしているってこと。
だからこそ撮ってみたわけだけど‥‥大して面白くもないわね。
「ん? ルナ、それなーに?」
突然、無邪気な瞳がひょっこりとレンズを覗き込んできた。
「あら、ノア。カメラよ。デジタルビデオカメラ。映像を記録してるの」
「えいぞーを、きろく‥‥?」
「おい、ルナ。ノアにそんな難しいこと言ってもわかんないぞ」
眉根を寄せて首を捻るノアの頭を、軽く叩くようにして手を置くAg。
二人の身長差は40センチ近くもある。並ぶとまるで大人と子供だ。
ノアは華奢で小柄。
Agは筋肉質で大柄。
純朴なノアに対して、Agはちょっと乱暴。
イエネコとヤマネコみたいな二人だ。
猫の耳と尻尾も生えてることだしね。
「あっれェ? きみたち何してるんだい?」
不意に聞こえてくる、突き抜けて明るい声。
振り向くと、派手な服装の少年が一人。
彼の名前はQ。
顔立ちはとても端正で、頭脳も飛び抜けて明晰だけど、珍奇な格好と言動が全てを台無しにしている変わり者だ。
けれどその振る舞い故に、彼は疎まれも憎まれもせず、誰とでも上手く付き合っている。
陰で『狂犬』なんて言われてる私とは大違いだ。
「撮影よ。この間、人間の輸送隊を襲った時の戦利品にあったやつ」
「アッハぁ〜ン☆ なんで真っ先にボクに声を掛けてくれなかったのさァ!」
くるりと回ってビシっとポーズ。
薔薇でも咥えさせたら似合いそう。もちろん棘付きだけど。
そんなことを考えつつも、私はQをフレームに収め続けた。
彼は飽きること無く次々とポーズを取っている。
「ところで、 でそんな してん ?」
────────────────────────
「ん? 音飛びしましたね」
「そうね」
「跳んでない場所も、時々聞き取り難いですね」
「贅沢言えないわよ」
「前後の発言からなんとなくは判りますが」
「エリック。五月蝿い。黙って見ろ」
「‥‥はい‥‥」
────────────────────────
忙しないQを横目に、Agが机の上に腰掛けながら訊いてきた。
「んー‥‥思い出作り?」
「はぁ?」
理解出来ないものを見る目で、彼は私を見る。
「なんだそれ」
「別に深い意味はないんだけど‥‥私達って、過去の記憶がないじゃん?」
「まぁな」
「ハーモニウムとして目が覚める前の生活がどんなだったか分からないけど、少なくとも『今』は楽しい」
「まぁ‥‥そうだな」
「だから」
「だから?」
「だから、残しておきたいって 。いつ死 わからない、い た消されるかわからない。だから」
「ふーん‥‥よっくわかんねぇな、俺には」
ぷらぷらと長い脚を泳がせながら、Agは興味なさそうだ。
その気持ちは、よくわかる。
だって、私にすらこの気持ちは、よくわかっていないんだから。
──‥‥‥‥──‥‥──‥‥‥‥──
「これでよし、と。スプーンとフォークは全員に 渡ってるよね?」
「ウィルカ、すま アがスプーン落とした」
「 了解。──はい、ノア、新しいスプーン」
「ありがとウィルカ。ごめんね」
「いいよそれくらい」
褐色の肌の、幼さを多少残した中性的な顔立ちの少年は、柔らかく笑ってノアの頭を撫でる。
しょげていたノアは、ウィルカに撫でられて心地良さそうに目を細めていた。
私たちは今、基地の屋上でピクニックシートを広げてのお茶会の最中だった。
ウィルカお手製の紅茶とお菓子──ケーキやクッキー、プリンなどが、皆の前に並べられている。
既製品は人間の輸送車輌を襲えば割と簡単に手に入るけど、手作りする為の器具や材料が手に入ることは滅多にない。
だから今日のお茶会は、結構貴重だった。
「いつまで撮ってますの?」
皆がシートに直接座っている中で、居丈高な口調の彼女だけは、何故か上等な椅子に座っている。
フィディエル。
皆からはフィディとかフィーとかって呼ばれている。
私とは犬猿の仲‥‥とまではいかなくても、あまり気が合うとは言えない。
実験の所為か元々の性質なのかは判らないけど、ころころと人格の入れ替わる彼女と真っ当に付き合うのは至難の業だ。
しかも基本的には酷い嗜虐趣味だし。
見た目が常軌を逸した美しさなのは認める。
けど、それを差し引いて余りある扱い難さだ。
何故ウィルカはこんな少女に忠誠を誓っているのか。
はっきり言って正気を疑う。
「いつまでもなにも、一通り撮るつもりだけど」
「悪趣味っスなぁ」
「あんたに言 」
「 はっ、その通 ね♪」
頭痛がする‥‥
「フィディエル、はい、ケーキ」
私たちのやり取りを気にすることもなく、切り分けたケーキを乗せたお皿を、ウィルカが穏やかな微笑を湛えてフィディエルに差し出す。
すると彼女は何を思ったのか、素手でケーキを掴んで食べ始めた。
もちろん手はクリーム塗れだ。
あの子、本気でおかしいんじゃないの‥‥?
私が割と真剣に訝っていると、
「ほら、綺麗にしないさい、犬」
食べ終わるなり、やにわにウィルカに呼びかけて、手を伸ばした。
え? まさか?
と思うや否や、ウィルカは苦笑とも微笑ともつかない微妙な表情で、フィディエルの手についたクリームを恭しい仕草で舐めとり始めた。
──だめだ。あっちの世界は理解できない。
彼女と仲良くなれることは一生ないな、と思いつつ、他を映すことにした。
銀髪の双子は、静々と上品にケーキと紅茶を嗜んでいる。
「‥‥甘い‥‥美味しい‥‥」
地面に渦巻くほど髪の長いヘラは、どこかぼんやりとした口調で呟いた。
「俺の分も食べるか?」
赤い瞳に優しげな光を宿すシアは、半分ほど残っているケーキを妹に差し出す。
「お兄様は、もう食べないの?」
「あぁ」
「‥‥じゃあ、貰う 」
儚く仄かに微笑んで、ヘラはケーキを受け取って嬉しそうに頬張った。
うん。美しい光景だ。
映像として記録に残すなら、こういうのを選びたい。
爛れた関係なんて映すんじゃなかった。
容量が勿体ないったらないわよ。
カメラは向けずに視線だけでちらりと見ると、フィディエルの元にウィルカの姿はなくて、彼女は退屈そうに頬杖をついていた。
その視線の方向にカメラを向ける。
ウィルカとQが、和やかに談笑していた。
フィディエルに対するウィルカの感情は崇拝や忠誠だと思うけど、Qに対しては尊敬と親愛を抱いているように見える。
事実、ウィルカは何かとQを頼ることが多い。
「あれで変態じゃなければ、私も素直に尊敬できるんだけどなぁ‥‥」
思わず口に出してぼやいていた。
フィディエルもそうだけど、ナルシスト気質な相手はあまり好きじゃない。
けれどそれを踏まえても私は、彼らを大切に思う。
これが元は植え付けられた感情なのは薄々わかっているけれど、種に水と栄養を注いで育んだのは私たち自身だ。
Qが中身の入ったカップを手に持ったまま奇抜なポージングをして、舞い散った飛沫が掛かったウィルカが楽しげに苦笑している様を見ながら、そんなことを取り留めもなく考えるのだった。
──‥‥‥‥──‥‥──‥‥‥‥──
「ディアナ」
私の呼びかけに、長い銀髪を揺らして彼女は振り返った。
髪が揺れるのと同時に、学生服の下で胸が揺れているのも気になるところだけど。
同じものを食べてるのに、なんでこんなに差が‥‥?
自分の胸部を目線だけで見下ろして、少し悲しい気持ちになる。
視線は床まで一直線だ‥‥
「‥‥どうかしたか?」
呼び止めておきながら沈黙する私を、僅かに訝しんだ瞳で見るディアナ。
向けられているカメラのことは、特に気にならないようだ。
「ごめんごめん。えっと、今度の『課題』、私たちの班に入らない?」
「構わないが、他に誰がいるんだ?」
「QとJ・B、フィディエルにウィルカ、Agとノア、シアにヘラ、それに私とアル、だね」
「随分と豪華だな。そんなに難題だったか?」
「襲撃対象が割と規模の大きな輸 その中身がね、ちょっと独占したくて」
「嗜好品だな?」
「ご明察」
「恐らく、サルヴァドルとファルコンも同行 たが 思う 」
「足手まといにならない限りは、構わないわよ」
「それなら心配は無用だろう。彼等もハーモニウムだ」
「じゃあ決まり。今夜、第二会議室を借りて打ち合わせするから、21時くらいに来てね」
「了解した」
頷くと、ディアナは優雅な身のこなしで踵を返し、歩いて行った。
その背中をなんとなく見送っていると、曲がり角の直前で彼女は振り返った。
「ところで‥‥そのカメラはなんなのだ?」
「今頃? えっと、なんか撮影するのが癖って 趣 になっちゃって」
「ふぅ うしてるとニンゲ カメラマンみたいで、あまり印象は良くないと思うぞ」
そう言い残すと、ディアナは再び私に背中を向けて、廊下を曲がって行った。
「‥‥ま、わかってるんだけどね」
それでも撮らずには、残さずにはいられない。
衝動の根源が何に起因するのか解らないけれど。
──‥‥‥‥──‥‥──‥‥‥‥──
響く悲鳴。
轟く爆発音。
引き裂く銃声。
阿鼻叫喚の地獄絵図──人間に取っては、ね。
アウカ・ルナからカメラを託された僕ことウィルカは、レンズ越しに戦闘の様子をつぶさに観察していた。
近頃は肌身離さずカメラを持っていたルナだけど、根っからの好戦的な気性が撮影への執着に勝ったみたいだ。
琥珀色の髪を振り乱し、彼女特製の鎖鎌で人間を次々に葬り去っている。
その傍らでは、メチャクチャな配色に髪を染めたざんぎり頭のアル・マヒクが、「皆殺しだオラァ!」と叫んで銃を乱射していた。
暴れているのは勿論、二人だけじゃない。
Qは得体の知れない合成キメラを操って人間を蹂躙してるし、ディアナは3メートルはあろうかというハルベルトを振り回して人間を薙ぎ払ってるし、ヘラは虎の白玲と共に人間を駆逐してるし、フィディエルは愉悦に満ちた笑い声を上げながら人間を引き裂いている。
うん。これは戦闘じゃないな。虐殺だ。
みんな頑張ってるなー。
Qの立案した作戦がぴったりと嵌ったお陰で、輸送隊は能力者の護衛をつけていたにも関わらず、一〇分と持たずに全滅していた。
当然、こちらの損害はゼロ。
怪我とも言えない軽傷を負っただけ。
「やーっ! すっきりしたー!」
真っ白だったワンピースを返り血だけで真っ赤に染めて、フィディエルが満面の笑顔で戻って来た。
カメラに向かってVサインをするほどご機嫌な様子。
彼女ほどじゃないにしても、皆もそれなりに機嫌は良さそうだ。
と思いきや、立役者のQだけが浮かない顔をしていた。
「どうしたの?」
訊ねる僕に対し、大袈裟なジェスチャーで悲嘆を表しながら、
「ボクの妖精(フェアリィ)ちゃんが、使い物にならなくなっちゃったんだよォ」
見れば、さっきまで縦横無尽の大活躍をしていた合成キメラは地面に倒れ伏し、小刻みに痙攣していた。
口から泡まで吹いている。
「でもまぁ失敗しちゃったのはしょうがないから、今日のデータを次に活かさないとネ☆」
僕にウィンクされても困るんだけどなぁ。
「ウィルカ、ありがと」
好き放題に暴れ回った興奮で頬を桜色に染めたルナが、小走りに寄ってきて手を伸ばす。
カメラを差し出すと、彼女は大事そうに受け取って、今し方撮れたばかりの映像を確かめ始めた。
扱いなんて解らないから、なんとなく皆が戦ってる様子を映してただけなんだけど、どうやら彼女は満足したらしい。
「うん、ばっちり」
狂気じみた表情で鎖鎌を振るう時とは正反対に、ルナは爽やかに微笑んだ。
ちょっとドキっとする。
「ウィールカー」
「はひっ!?」
フィディエルの不機嫌な声で心臓が飛び跳ねた。
「着替え」
さっきまでの上機嫌は何処へやら、不愉快さ満点の表情で彼女は言い捨てる。
「ごめん。行くね」
──そう言い残してフィディエルの元へ走るウィルカを、私は苦笑いで見送った。
尊大な態度の少女の返り血塗れのワンピースを脱がせ、替えの新しいワンピースを着せている。
フィディエルの裸なんて撮る気にもならないし、他の皆を撮ろうかな。
返してもらったカメラを早速構えて、レンズを巡らせる。
ヘラは白玲の背中を撫でながら寛いでいて、シアは黒馬の上で静かに遠くを見ている。
いや、戦利品の物色しようよ。
って、私もサボってるんだった。
カメラ片手に、輸送車の方へ向かう。
荷台には既にAgとノアが上がっていた。
「どう?」
「大漁だな」
「ココア ! バー ーヘンだー! お肉だー!」
「 らノア、今食べんじゃねーぞ。勝手に食ったら先生に叱ら らな」
「むー、わかってるよそれくらいー」
子供みたいにふくれっ面になるノアだけど、今にも涎を垂らしそうな勢いだ。
Agに嗜められなかったらつまみ食いしてたに違いない。
それにしても、あんまり人間寄りな嗜好は覚えない方がいいと思うんだけど、大丈夫なのかなぁ。
カメラマン気取りになった私が言うのもなんだけどね。
「ルナ、ファルコンがプロテインはあるかと五月蝿いんだが、探してもらえないか?」
荷台の入り口で、ディアナが若干ばかり辟易した声音で訊いてきた。
確かに、外でがーがー言ってる声がする。
「んー、ちょっと待ってね」
それらしい一角の段ボール箱を漁ってみるが、見当たらない。
「なさげかも」
「──ファルコン、今回は外れだそうだ」
「おのれニンゲンどもめ! プロテインを運ばんとはどういう了見だ!」
苛立たしげに吠える大男だが、言い掛かりも甚だしいので放っておくことにする。
「ルナ、炭酸あっか?」
今度はアルが訊いてくる。
自分で探せよとも思ったが、ただでさえ荷物でいっぱいの荷台に、これ以上は乗れないのも事実だった。
「んー‥‥あるけど、あんま冷えてないよ?」
「ちっ。お預けかよ」
「っていうかあんた、あれ飲むと気 悪い ンション上がってウザイからやめて欲しいんだけど」
「あ? っせーな。オレの勝手 よ」
この男はほんとにもう‥‥
殴りたい衝動に駆られたが、今暴れると戦利品が木っ端微塵になる可能性があるのでなんとか我慢した。
偉い。私偉い。すごい。
「運転は誰がする?」
自画自賛に浸っていると、馬上のシアが言葉を投げかけてきた。
「あ、私するよ。アルは助手席ね」
「あ!? なんでだよ!?」
「一人だと寂しいじゃん」
「くそっ。わぁーったよ、ったく‥‥」
悪態を吐きながらも押し問答するでもなくあっさりと助手席に向かう彼が好きだ。
私も荷台から降りて、運転席に乗り直す。
まだぶつぶつ言ってるアルを肘で一度だけ小突いてから、私は差しっぱなしのキーを回して、エンジンを掛けた。
私の記憶は、そこで途切れた。
──‥‥‥‥──‥‥──‥‥‥‥──
「長期休眠、だってさ」
僕が告げると、皆はそれぞれの度合いでほっとして見せた。
「まさ 間に嵌め んてな‥‥」
Agが怒りを押し殺した表情で言葉を搾り出す。
あの日、僕らが襲撃した輸送隊は、罠だった。
車両に仕掛けが施されており、ルナがエンジンを掛けると同時にトラックは爆発した。
勿論、僕たちだって無事じゃなかった。
けれどなにより、突然の爆発で混乱する渦中に、追い討ちを受けたのが不味かった。
まさか仲間の死まで織り込み済みの作戦なんて、誰が気づけただろう。
故に伏兵として現れた能力者連中の攻勢は熾烈を極め、僕たちは各々が自分の身を守るのが精一杯で、アルとルナの二人を助ける余裕なんてなかった。
──いや、一人だけ、いた。
Q。彼だけが己が身を顧みずに、二人を助けてくれた。
だから辛うじて、一命を取り留めることができたんだ。
そのことについてJ・Bは烈火のごとく怒ったが、それも最もだろう。
殆ど自殺行為に等しい狂行だ。
よく誰も死なずに済んだと思う。
当のQはと言えば、
「んっふふ〜。みんな無事で良かったよねェ。物資が全部吹っ飛んじゃったのはもったいなかったけど☆」
などとあっけらかんとしているのだから、流石としか言いようがない。
「なんにせよ、この借りは返さないとな」
寄り添うヘラの髪を梳きながら、シアが言う。
「そうだね。多分、もうすぐ実戦 され と思う その時に思い知らせよう」
「はっ。上等よ。こっちは散々待ちくたびれたってーの」
拳を打ち鳴らし、フィディエルが凶悪な笑みを浮かべる。
心配する素振りすら見せないけど、彼女がどれほど二人の安否に気を病んでいるかを、僕は知っている。
「民間人軍人能力者の区別なく、全員まとめて嫐り殺してやりますわ‥‥!」
「フィーは相変わらず過激だな」
「な 句ありますか? Agさん」
「いーや、なんにも。ま、俺は俺のやりたいようにやるさ。 殺す け なん しさ」
「ノアはおいし ものが食べたい! ルナとアルが起きた時の に、おいしーもの集めようよ!」
「欠食児童が‥‥」
小馬鹿にしながら、フィディエルはノアの額を指で弾いた。
「ぃったーいー! フィーなにするのさっ! ひどいっ!」
「っさい! だぁらっしゃい!」
「ノアに当たんなよ、ヒス女」
あぁAg、そんな火に油を注ぐようなこと‥‥
「‥‥ ら殺してもいいのよ?」
「はいはい、ご勝手に。できるもんならな」
二人の間で殺気が膨れ上がる。
ディアナたちは我関せずと退避して、シアとヘラは最初から傍観の構えだ。
どうやって矛先を収めてもらおうかと僕が狼狽えていると、
「おっ、やっと映った! 流石ボク! 天っ才だなァ〜♪」
空気を読まないどころかぶち破る明るい声が響いた。
渡りに船とばかりに、僕は飛びつく。
「な、何が映ったの? って、それ、ルナの持ってたデジカメ?」
「ご名答☆ さっすがウィルカたん♪ 撮影は機能してたんだけど、ディスプレイが映らなかったんだよねェ。ルナたんが身を呈してまで庇った物だから、壊れたまんまじゃ忍びないからネ☆」
誰にともなくウィンク。
呆けたような空気が流れたお陰で剣呑な雰囲気は霧散し、フィディエルとAgの衝突は取り合えずは避けられた。
「それにしても、よくあの爆発と襲撃の中で無事だったね」
「必死に守ったんじゃないかなァ」
Qの手の中のデジカメは傷だらけだが、確かに動いている。
「ま、取り合えずはボクが預かるよォ。折角だから中の映像も保存しておきたいしネ。異論はない?」
「勝手にすれば」
言い捨てるフィディエルに、Qはにんまりと微笑んで見せた。
「オッケーィ。じゃあ早速撮影代理としての初仕事しちゃおっかなァ〜♪」
宣言するなりQはカメラを構え、フィディエルを映し始めた。
「ちょっと、なに?」
「二人が目覚 時の為に、メッセージを残し おこ 思ってサ☆ はい、一言どうぞォ〜」
「はぁ? よそれ?」
「ほらほら早くゥ」
「もうっ、わかったわよ! ──えっと、その、あれよ! 起きたなら、さっさと会いに来な !」
「ん〜、実にフ ィらしいネ☆ 次、ウィルカたんっ」
「えーっと‥‥無事、ではないけど、生きてて良かったよ、二人共。元気になったら、また一緒に遊ぼうね」
「いいねいいねェ。じゃあ次はディアナたん行ってみようかっ」
「私か? ふむ‥‥完治したのなら、早く前線に出てくるんだな。お前らの戦力は必要だ」
「んっふふ〜、痺れちゃうなァ! 次はファルコ‥‥てあれェ? サルヴァドルたんもいないねェ」
「二人なら、さっき出ていったぞ」
「そっかァ。じゃあ後回しだね。気を取り直して、シアたんとヘラたんいってみよう!」
「特 言うこともないんだが‥‥快癒おめで 。恨みを思い切り晴らすといいさ」
「‥‥回復、おめでとう。また頑張ろうね」
「シンプル・イズ・ベストってやつだネ! じ 、Agたんとノアたんっ」
「助けられなくて悪かったな。この借りは返すからよ。また会おうぜ」
「イタイのたいへん よねっ。ノアがんばってツヨクなるから、いっしょに戦おうねっ」
「良 メントだよォ。二人とも喜ぶ 間違いなしカナ♪ 最後はJ・B、どーぅぞ☆」
「えっと‥‥あんたらみたいのでも、 と落ち着かないから、早く戻ってきてよね」
「素直じゃないなァ、J・Bは☆」
「悪かったわね」
「Q、カメラ貸しなさいよ」
にまにましているQに歩み寄り、フィディエルが手を伸ばして催促した。
「ん? なんでだい?」
「あん コメント、撮ってないでしょう?」
「ふっふーん、それはね?」
不敵に笑い、ひらりと身を翻すQ。
「後で一人でこっそり撮るのさァ〜♪ それじゃあまた明日ね、みんな!」
「あ、ちょ!」
疾風のごとく走り去るQ。
意表を突かれたのと、必要性を感じなかったのとで、誰も追いかけはしなかった。
「相変 だな」
「だねー」
Agとノアの呟きが、皆の気持ちを代弁していた。
──‥‥‥‥──‥‥──‥‥‥‥──
「さて、と。
やあ、アルとルナ。
これを見てるってことは、元気になったってことだよね。良かった。
っと、ルナ、ごめんね。大事なカメラ、勝手に弄って。
お詫びと言っちゃなんだけど、映像は全部大切に保管してあるから、安心していいよ。
場所は、そうだね‥‥ボクに会いに来てくれたら、教えてあげるよ。
それくらいの余興、許してくれるよね? ふふ。
──いやぁ、カメラに向かって一人で喋るのって、流石のボクでも恥ずかしいねェ。
話したいことは色々あるんだけど、会ってからの楽しみに取っておこうか。
その頃にはボクの研究もきっと完成してるだろうから、驚かせちゃうゾ☆
畏まった割に短くなっちゃったけど、この辺で切り上げることにするよ。
みんな、きみたちと会えることを楽しみにしてる。
これを見たら、頑張って会いに来てよネ♪
それじゃ、締めはこの言葉で。
『おはよう、親愛なる学友たち』──」
──‥‥‥‥──‥‥──‥‥‥‥──
奇妙な静寂が研究室を支配していた。
ごくり、と唾を飲み下し、エリックは額の汗を拭う。
イヤな、汗だった。
「‥‥どうするんですか、これ」
「──どうもしないわよ」
「どうもしないって」
「このまま公表することになるでしょうね」
「‥‥いいんですか‥‥?」
「私が判断することじゃないし」
「それはそうですが‥‥」
「判断は、軍と──能力者たちがするのよ」
すっかり冷めて不味くなったコーヒーを啜り、秋桜理は不愉快そうに溜息を吐いた。
胃の底に、得体の知れない沈殿物の存在を感じる。
その正体に、彼女はまだ、気づいていない。
<執筆:間宮邦彦>
|
|
 |
 |
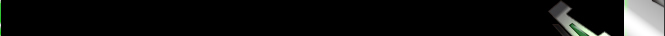 |